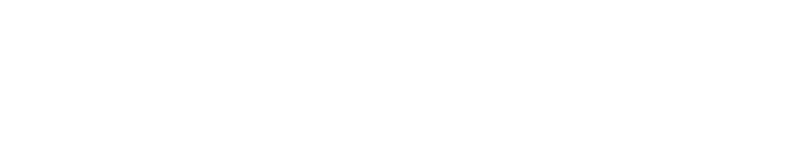セントラル空調とは、ビル全体の温度を一括で管理できる空調で、運転時のエネルギー効率も良く、大規模な建築物などで多く採用されています。
しかし、すべての建物に最適というわけではなく、状況によっては部屋ごとに調整可能な個別空調の方が適しているケースもあります。
そのため、導入時には用途や運用方法を十分に検討することが大切です。
本記事では、セントラル空調について紹介していきます。
他にも「セントラル空調でエアコンを集中管理するメリット・デメリット」や「個別空調でエアコンを管理するメリット・デメリット」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、セントラル空調について理解を深めてみてください。
セントラル空調とは?

セントラル空調とは、建物内の空調を効率よくおこなうために、冷凍機やボイラーといった熱を生み出す装置を一か所にまとめて配置し、全体に冷暖房を供給するシステムです。
熱源設備が中央に集められているので、「中央式空調」とも呼ばれます。
また、空気や温水がダクトや配管を通じて各スペースへと運ばれるため、「ダクト式空調」とも呼ばれることがあります。
主に、延べ床面積が1万平方メートルを超えるような大規模な建築物で利用されており、具体的にはショッピングモールやホテル、商業ビルなどが導入の対象となっています。
一般的な空調との違い
空調方式には大きく分けて、建物全体を一括で制御する「セントラル空調」と各部屋やエリアごとに独立した設備を設置する「個別空調」があります。
個別空調では、ルームエアコンやパッケージエアコンなどが機器として用いられており、主に一般家庭や延べ床面積10,000㎡未満の中小規模のビルで広く導入されています。
一方で、セントラル空調を導入している建物では、空調管理を一括しておこなうことが多くなっています。
しかし、建物の構造や利用形態によっては、セントラル空調と個別空調の両方を併用するケースもあります。
セントラル空調でエアコンを集中管理するメリット

メリットについては、以下の5つが挙げられます。
- 設計の自由度が高い
- メンテナンス費用を抑えられる
- 温度を均一に保てる
- 静音性が高い
- スペースを有効活用できる
それぞれのメリットについて解説していきます。
設計の自由度が高い
セントラル空調システムは、冷水や温水を建物内の各階へ水配管で供給し、それを利用して冷暖房をおこなう仕組みなので、設計の自由度が高いメリットがあります。
具体的には、水配管の距離や高さに関する制限がほとんどなく、超高層ビルや大型商業施設のような大規模建築でも高い空調効率を発揮できます。
一方で、パッケージ型の空調システムは冷媒を循環させて冷暖房をおこないますが、この冷媒を通す配管には長さや高低差に制約があるので、主に個々の部屋や階ごとに設計・設置されるのが一般的です。
メンテナンス費用を抑えられる
セントラル空調方式は、建物内の熱源機器を一か所にまとめて管理する構造のため、全体的な保守・点検にかかる費用を抑えることができます。
一方、パッケージ型の空調設備は、各部屋やフロアごとに独立して設置されているため、それぞれに対する保守対応が必要となり、作業の手間がかかる上、冷媒の取り扱いなど専門的な知識も求められることから、結果的にコストが膨らむ傾向にあります。
また、製品や使用状況により異なりますが、セントラル空調は適切な管理を行えば30年近く使用可能なケースもあります。
このように、個別空調よりもセントラル空調の方がメンテナンス費用を抑えることができます。
温度を均一に保てる
セントラル空調システムは、建物全体の空調を集中管理する方式であり、室内の温度を均一に保つことができるメリットが挙げられます。
実際に、一元的な管理をすることによって、エアコンのスイッチの切り忘れといったミスを防げる点も大きなメリットです。
そのため、決まった時間帯に空調を使用するオフィスや医療施設、商業施設などで特に有効です。
静音性が高い
セントラル空調は、静けさも大きな魅力の一つです。
空調設備が建物の内部ではなく、屋上や地下など居室から離れた場所に設置されるので、運転音がほとんど室内に届かないので、快適で静かな空間が実現できます。
高い静音性は、音に対する配慮が特に重要な図書館や映画館などでも高く評価されており、多くの施設で採用されている実績があります。
スペースを有効活用できる
セントラル空調は、熱源を一か所に集中させることで、管理に必要なスペースも同様に一か所に集約でき、効率的な運用が可能になるメリットが挙げられます。
また、個別空調のように各部屋ごとに熱源装置や換気設備を設置する必要がないため、室内の空間を有効に活用することができます。
また、パッケージ型空調のようにフロアごとに空調設備を分散して配置する必要がないので、設備に割くスペースを抑えることができ、空間設計の自由度が高まります。
さらに、建物の外観に多数の室外機が並ぶこともなく、外観の美しさを維持することにもつながります。
セントラル空調でエアコンを集中管理するデメリット

デメリットについては、以下の4つが挙げられます。
- 初期費用が高額になる
- 細かな運転や設定ができない
- 故障するとコストが高い
- 光熱費が割高になる場合がある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
初期費用が高額になる
セントラル空調でエアコンを集中管理するデメリットとして、初期費用が高額になってしまうことが挙げられます。
具体的に、セントラル空調は個別空調とは異なり、空気を各部屋に送るために天井や壁の内部にダクトや配管を通す必要があります。
そのため、建物の建設時に導入する場合でも、設置コストが高くなりがちです。
また、後からセントラル空調を導入しようとすると、大規模な改修工事が避けられません。
細かな運転や設定ができない
セントラル空調は、建物全体を一括で管理できますが、細かく運転や設定をおこなうことができないデメリットが挙げられます。
例えば、広大なフロアに複数の空調機が設置されている場合、窓際と中央部分では日射や外気の影響により体感温度が異なることがあります。
しかし、セントラル空調では、そのような局所的な温度差に対して、ユーザーが任意に温度や風量を調整することができません。
そのため、単一の利用目的で運用されるオフィスビルのような施設では、セントラル空調が効率的ですが、フロアや部屋ごとに用途が異なるテナントビルでは、個別空調の方が適していると言えます。
故障するとコストが高い
故障が発生した場合、修理費用が高額になってしまうデメリットが挙げられます。
また、空気を運ぶダクト部分に問題が生じた際には、天井や壁を一部解体して対応しなければならないこともあり、追加の工事費が発生する可能性もあります。
特に、熱源装置の不具合によって、建物全体の空調が一時的に止まることもあり、その修理には専門的な対応が必要となります。
このようなトラブルを防ぐためには、機器の状態を定期的に点検することが重要です。
光熱費が割高になる場合がある
セントラル空調でエアコンを集中管理するデメリットとして、光熱費が割高になってしまうデメリットが挙げられます。
個別に空調を管理できるシステムでは、それぞれの部屋でエアコンの電源を自由に切り替えができるので、光熱費を抑えることが可能です。
一方、セントラル空調では、建物全体が常に冷暖房される仕組みのため、利用していない部屋にも無駄にエネルギーが使われてしまいます。
特に、家族や社員が一部の部屋に集まる傾向がある場合、使用しない部屋の空調まで稼働してしまう結果、光熱費が高くなってしまうケースが見られます。
個別空調でエアコンを管理するメリット

メリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 設定を自由に変更できる
- 電気料金の無駄を省ける
それぞれのメリットについて解説していきます。
設定を自由に変更できる
個別空調のメリットとして、フロアごとに空調の調整が可能です。
必要なスペースのみ空調を稼働できるので、休日や夜間など利用者が少ない時間帯には、使わない部屋の空調を止めることで、電気代の節約につながります。
冷暖房の切り替えに加え、風量や温度の細かい設定も行える場合が多く、快適な環境作りが可能です。
しかし、すべて物件が個別空調設備を設置できるとは限らないので、物件選びの際には仕様の確認が必要です。
電気料金の無駄を省ける
個別空調でエアコンを管理するメリットとして、電気料金の無駄を省けることが挙げられます。
スイッチ操作でいつでもON・OFFの切り替えができるので、使用していない部屋の電源を切って電気代の節約が可能です。
また、特に時間制限なども設けられておらず、基本的に一日中利用することができます。
個別空調でエアコンを管理するデメリット

デメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 使用方法で消費電力が増えてしまう
- 設置できない建物もある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
使用方法で消費電力が増えてしまう
個別空調では、使った分だけ光熱費が発生するので、消し忘れたり、長時間にわたって極端な設定で使用してしまうと、電気代が大幅に増えてしまう可能性があります。
また、操作の自由度が高いことから、冷暖房を必要以上に使ってしまう傾向があり、結果的に増えてしまう原因にもなります。
実際に、快適さと経済性のバランスを保つためには、利用者側の配慮が求められます。
セントラル空調がおすすめの建物

セントラル空調がおすすめの建物については、以下の2つが挙げられます。
- オフィスビル
- ホテル
それぞれの項目について解説していきます。
オフィスビル
セントラル空調がおすすめの建物として、人の出入りが頻繁で、面積の広いオフィスビルが挙げられます。
一般的に、延床面積が1万平方メートルを超えるようなオフィスビルでの導入が有効とされています。
しかし、同じオフィスビルであっても、その用途によってはフロア単位で個別空調を併用するケースもあります。
例えば、在宅勤務やフレックスタイム制度を取り入れている企業では、勤務時間や人の動きに応じて調整しやすい個別空調の方が、柔軟性という点でメリットがあると言えます。
このように、オフィスビルでは広範囲にわたって温度や空気の管理が求められるので、中央で一括制御できるセントラル空調がおすすめと言えます。
ホテル
セントラル空調がおすすめの建物として、ホテルが挙げられます。
ホテルで空調を一括管理することによって、管理コストや品質を維持することにもつながります。
しかし、ホテルのロビーや部屋などそれぞれ異なる温度設定が求められる場面が多くありますが、セントラル空調でも「ゾーン制御」や「ビル管理システム(BMS)」を導入することで、各エリアに適した温度環境を実現できます。
ゾーン制御とは、サーモスタットや可変風量装置(VAVシステム)を組み合わせて、フロアごとやエリア単位で風量や温度の調整を行う仕組みです。
セントラル空調でもこのような制御を行うことで、一括管理しながらも細やかな温度調節が可能になります。
そのため、ホテルのように利用目的が多様な空間であっても、ゾーン制御やBMSを活用して設計・運用すれば、快適で効率的な空調環境を提供することができます。
建物に合った空調を選ぼう!

今回は、セントラル空調について紹介しました。
空調システムには、大きく分けて個別方式とセントラル方式の2種類があり、それぞれ熱源の配置や管理方法に特徴があります。
セントラル空調は、建物内にひとつの熱源設備を設け、空調の運転や制御を集中管理する仕組みで、施設全体を統一的にコントロールしたい場合に適しています。
一方、個別空調は、各部屋やエリアごとに温度調整が可能なので、フロアごとや細かいエリア単位で柔軟な温度管理が可能です。
どちらの方式を採用するかは、建物の規模や使用目的、空調に求める快適性などを踏まえて、最適な方法を選ぶことが求められます。
今回の記事を参考にして、建物に合った空調を選ぶようにしましょう。