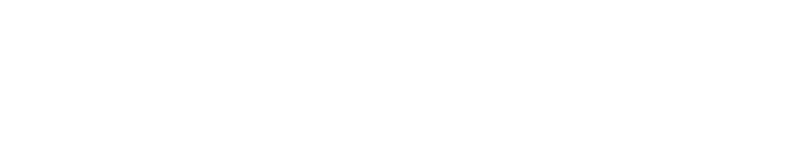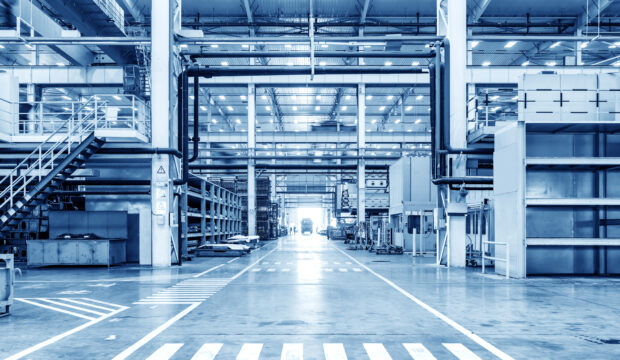BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)は、建物内で使用されるエネルギーの使用状況を記録・解析する仕組みです。
このシステムを活用することで、蓄積された情報をもとにエネルギーの使い方を見直し、無駄を減らしてより効果的な活用方法へと段階的に改善することが可能になります。
本記事では、BEMSとBAS(中央監視システム)との違いを紹介します。
他にも「BEMSを導入することのメリット・デメリット」や「BEMSの導入事例」について解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、BEMSとBAS(中央監視システム)の違いについて理解を深めてみてください。
BEMSとは?

BEMS(ビルエネルギー管理システム)とは、建物全体のエネルギーの使用状況を一括して監視・管理し、効率的なエネルギー活用と快適な室内環境の両立を目指す高度な管理システムです。
正式名称は「Building Energy Management System」で、多くのオフィスビルや商業施設などに導入が進んでいます。
空調や照明といった設備の制御を通じて、エネルギー消費の削減と環境性能の向上が期待できます。
例えば、オフィスビルでは、各フロアに設置された人の動きを検知するセンサーや温度・湿度を計測する装置からの情報を中央の監視システムに集約することで、リアルタイムで最適な空調や照明の運転が可能です。
このように、BEMSの導入によって、無駄なエネルギー消費を抑えつつ、建物全体の快適性と省エネ性をバランス良くさせることができます。
BEMSとBAS(中央監視システム)との違い

BAS(中央監視システム)とは、照明設備や空調機器、防犯システム、電力量計などのさまざまな機器をネットワークでつなぎ、一括して監視・操作できるようにするシステムのことです。
多くのオフィスビルではこのBASを活用することで、快適な室内環境を保ちつつ、管理の手間を軽減しています。
BEMSとBAS(中央監視システム)との違いについては、以下の4つが挙げられます。
- 目的
- 機能
- 監視対象
- 効果
それぞれの違いについて解説していきます。
目的
BEMSは、建物内で使用されるエネルギーを効率的に管理・運用することを目的としたシステムです。
エネルギーの使用状況を「見える化」することで、空調設備や照明機器などの運転を最適に調整し、省エネルギーを図ることができます。
また、スマートコミュニティにおける重要な要素技術のひとつとされ、カーボンニュートラルな社会の構築にも寄与しています。
一方、BASは主にビル内の状態を監視・制御するシステムで、管理支援を目的としています。
各部屋に取り付けられたセンサーなどを通じて、室内の温度情報や設備の異常信号などを取得し、それらをもとに適切な対応をおこないます。
このように、BASはビルの快適性と安全性を維持するための監視機能を中心に構成されています。
機能
BEMSは、建物全体のエネルギー利用状況を「見える化」する機能を備えており、電力やガス、水道といった消費量をリアルタイムで把握することが可能です。
これにより、エネルギーの無駄遣いを洗い出し、改善策を導くための分析もおこなうことができます。
また、エネルギー使用量を最適化する機能も搭載されています。
さらに、消費パターンを基にした省エネ提案や実施した施策の効果測定、コスト削減の分析まで対応可能です。
BASについては、建物内の各種設備の監視・自動制御を中心に据えたシステムです。
具体的には、空調・換気・照明といった設備の運転を効率的に管理をおこないます。
空調制御では、室内環境を一定に保つよう自動で調整をおこない、照明に関しては人感センサーや明るさセンサーを活用して、無駄な電力使用を抑える仕組みが導入されます。
セキュリティ機能にも対応しており、入退室の管理や監視カメラとの連携を通じた総合的な安全管理を実現できます。
監視対象
BEMSは、建物内の多様なエネルギー利用状況を把握・管理するための仕組みで、主な対象は以下の通りです。
- 照明設備の利用状態
- 太陽光発電や蓄電池といった再エネ機器の運用状況
- 各種エネルギーデータの記録と解析
- 電気の使用量
- ガスや水道などのインフラ消費状況
- 空調および換気機器の稼働とエネルギー消費
BEMSはこれらの情報を収集・可視化することで、建物全体のエネルギー利用をリアルタイムで把握可能にします。さらに、分析されたデータを基に効率的なエネルギー利用への改善提案や、異常発生時の迅速な対応も可能になります。
BASの主な監視項目は以下の通りです。
- エレベーターやエスカレーターの動作状況
- 給水および排水システムの稼働状況
- 防災設備の監視とアラート機能
- 空調・換気システムの稼働状況
- 照明設備の状態管理
- セキュリティ関連の監視(出入り管理、防犯)
BASはこれらの設備が正常に機能しているかを常時監視し、ビル利用者にとって安全で快適な環境を維持することを目的としています。
効果
BEMSを活用することで得られる効果の一つとして、光熱費の大幅な削減が挙げられます。
建物内のエネルギー使用状況をリアルタイムで把握し、必要に応じて照明や空調などの設備を最適に制御する機能を持っているので、無駄な電力消費を抑えられ、光熱費全体を効率よく低減することが可能になります。
実際に、BEMSを取り入れた施設の中には、年間のエネルギー消費を10%以上削減できた例も多く見られています。
一方、BASを導入することで得られる主な効果として、建物の運用コストの削減が挙げられます。
BASは建物内の各種システムを自動で制御する仕組みで、使用状況に応じた照明や空調の調整をおこないます。
例えば、使用されていないフロアの設備を自動的にオフにすることで、エネルギーの浪費を防ぎ、運用にかかる費用を削減することができます。
また、BASは室内環境の快適さを保つことにも優れており、照明の明るさや室温を適切に調整できるので、建物内で働く人々の集中力や生産性が高まり、満足度の向上にもつながります。
BEMSを導入することのメリット

BEMSを導入することのメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 省エネ対策につながる
- 設備コストを抑えられる
- エネルギー使用状況を可視化できる
それぞれのメリットについて解説していきます。
省エネ対策につながる
BEMSを導入することによって、快適な職場環境を維持しながら、効率的にエネルギーを管理し、節電につなげることができます。
実際に、ビルにおけるエネルギー使用の内訳として、空調が約半分、照明が約2割を占めているケースが多く、エネルギーの大部分にBEMSが影響を与えることができます。
例えば、人の出入りが少ない時間帯やエリアでは照明や空調の稼働を自動的に調整することで、無駄を抑えた運用が可能です。
設備コストを抑えられる
BEMSを導入することによって、設備や建物の導入時にかかる初期費用だけでなく、その後に継続して発生する運用・保守などの費用も含めた、建物全体の設備コストを抑えることができます。
実際に、日常的にエネルギー使用量をモニタリングすることで、どの機器の性能が落ちてきているかを把握しやすくなります。
エネルギー効率が下がったり、老朽化が進んだ設備に対して、適切なタイミングで保守や更新をおこなうことにより、設備コスト削減につながります。
エネルギー使用状況を可視化できる
BEMSを導入することで、どの設備がどれだけ電力を消費しているかを詳細に把握できるメリットが挙げられます。
これにより、エネルギーの無駄や課題が明確になり、改善策を立てやすくなります。
また、改善の成果が数値で確認できるので、利用者の省エネ意識が高まり、継続的な改善活動につながります。
さらに、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」では、一定以上のエネルギーを使用する事業者に対してエネルギー使用の状況を把握し、届け出ることが義務付けられています。
そのため、BEMSは有効で、リアルタイムのエネルギー消費の把握やデータの蓄積が可能になり、目標の設定や改善活動、報告書の作成などがスムーズにおこなうことができます。
BEMSを導入することのデメリット
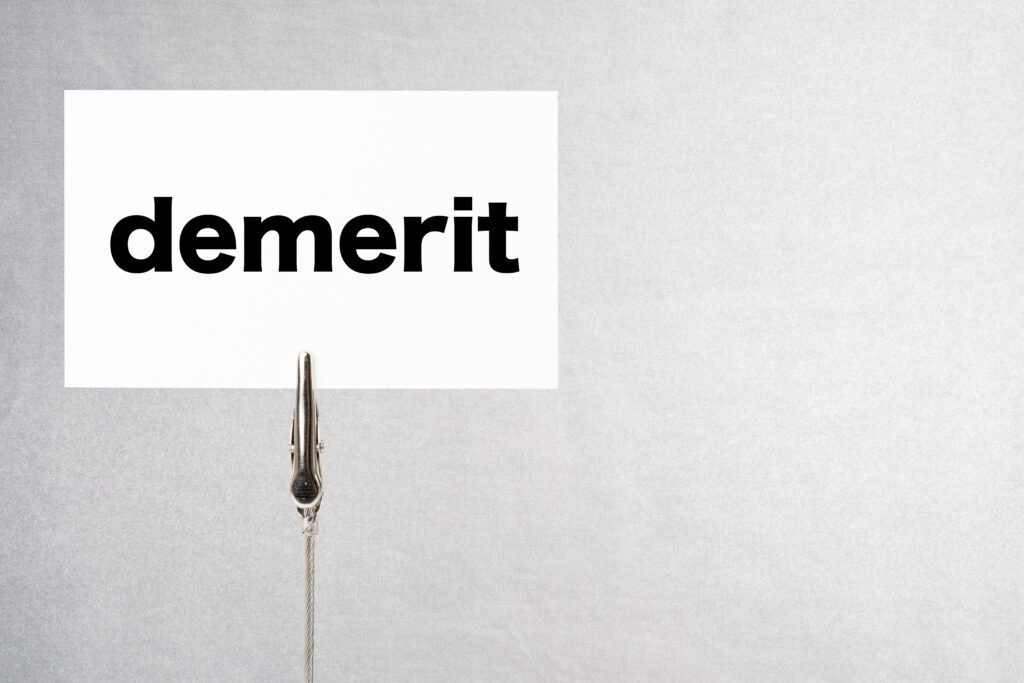
BEMSを導入することのデメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 専門的な知識が求められる
- 導入コストが高額になる
- セキュリティ対策が必要になる
それぞれのデメリットについて解説していきます。
専門的な知識が求められる
BEMSを効果的に活用するためには、専門的なスキルや知識が欠かせません。
単にエネルギーの使用状況を確認するだけでは、十分な省エネ効果やコスト削減にはつながりにくく、どのようにしてシステムを適切に制御・運用するかが重要です。
そのため、エネルギーの効率的な管理を実現するには、その分野に精通した専門家や豊富な実務経験を持つ人材の確保が不可欠になります。
導入コストが高額になる
BEMSを導入するデメリットとして、初期導入時のコストが高額になってしまうことが挙げられます。
運用後のコストは抑えることができますが、導入にかかる資金が過大であれば、全体の費用対効果が低くなってしまうリスクがあります。
実際に、導入の効果や必要な設備は、以下の項目によって大きく左右されます。
- 建物の規模
- 設置する機器の種類
- エネルギーを使用する時間帯
そのため、導入前には各条件に応じた詳細なシミュレーションを行うことが重要です。
万が一、自力での試算が難しい場合は、国や自治体が提供している無料のエネルギー診断サービスを活用することをおすすめします。
その際に、導入の可否や費用対効果について専門的なアドバイスを得ることも可能です。
セキュリティ対策が必要になる
BEMSをインターネット経由で活用する場合には、サイバー攻撃のリスクも考慮してセキュリティ対策が必要になります。
一般的なセキュリティ対策ではリスクが高くなってしまうので、高度なセキュリティ対策の整備が不可欠です。
また、安定運用を継続するための定期的な点検やトラブル対応の体制づくりも、導入前にしっかりと検討することが必要です。
BEMSの導入事例

BEMSの導入事例については、以下の3つが挙げられます。
- 高齢者施設
- 商業施設
- ビル
それぞれの事例について解説していきます。
高齢者施設
高齢者施設でBEMSを導入したことにより、電力の消費状況を可視化することができ、電力消費量の削減につなげることができた事例が挙げられます。
具体的には、BEMSによって施設の開館時に多数の機器を同時に起動していたことが、電力使用のピークを押し上げる要因を把握することができました。
このような課題に対応するために、開館直後に必ずしも必要でない機器については、稼働時刻をずらして順次起動させる運用へと改善を図ることによって、施設の契約電力を引き下げることに成功しています。
さらに、BEMSの導入は単なる設備管理にとどまらず、スタッフの省エネルギーに対する意識を高めることにも成功しました。
そのため、施設内で「不要な照明はこまめに消す」といった行動が習慣化され、日常的な節電の積み重ねが、電力消費量の削減に大きく寄与しています。
商業施設
商業施設にBEMSを導入することによって、営業時間に応じて空調の運転を自動で調整する仕組みを整えました。
導入したBEMSは、室内の温度や二酸化炭素濃度といったデータをリアルタイムで取得し、それをもとに空調の運転状況を最適化させることができます。
このような取り組みによって、来場者の快適な環境を保ちながら、電力の使用量を大幅に抑えることに成功しています。
ビル
BEMSを導入する以前のビルでは、耐震性の向上や省エネルギーに向けた取り組みは行われていたものの、エネルギーの使用状況をリアルタイムで把握する手段がなく、実際の省エネ効果を的確に評価することが困難でした。
このような課題を解決するために、BEMSの導入がおこなわれ、消費エネルギーの見える化を実現しました。
その結果、使用電力量や傾向を詳細に把握できるようになり、施策ごとの省エネ効果を定量的に確認できる体制が整いました。
さらに、BEMSの自動制御機能により、契約電力を超えないよう調整が可能となり、無駄な電力使用の抑制にも貢献しています。
自社の課題に合わせて最適なものを選ぼう!

本記事では、BEMSとBAS(中央監視システム)との違いを紹介しました。
BEMSは主にエネルギー使用の最適化を目的としたシステムであり、BASは建物内の設備を効率的かつ自動的に管理することで、快適な環境と安全性を確保する仕組みです。
これらのシステムは用途や目的が異なるので、建物の状況や管理の目的に応じて最適なものを選ぶ必要があります。
今回の記事を参考にして、自社の課題に合わせて適切なものを選ぶようにしましょう。